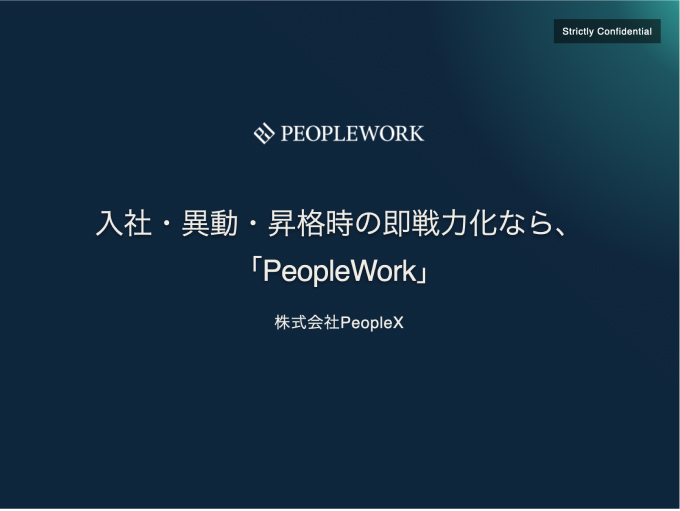2025.05.13
360度評価とは? 評価項目やメリット・デメリット、導入時のポイントを解説

360度評価は、人事評価を実施する方法のひとつで、上司だけでなく同僚・部下・他部署の関係者・顧客など、複数の視点から社員を評価する方法を指します。成果主義の広がりや働き方の多様化といった状況を受け、360度評価を導入する企業も増えています。
この記事では、360度評価の評価項目と実施手順、また、360度評価のメリット・デメリット、導入する際のポイントを解説します。
360度評価とは
360度評価とは、1人の評価者だけでなく、さまざまな立場にいる複数の評価者が評価を実施する評価手法のことです。
360度評価では、組織の上位に属する社員が下位の社員を評価する「垂直的評価」や、同じ立場の同僚同士で実施する「水平的評価」ではなく、複数人がさまざまな角度から評価を実施する「多面的評価」が行われます。
ここでは、360度評価を導入する目的と導入が進む背景を解説します。
360度評価を導入する目的
360度評価は、1人の評価者だけでは見えにくい部分についても評価を実施し、客観的で精度が高い評価を実現するために導入されます。複数の視点による評価がなされることで、1人の評価による場合と比べて主観による偏りを軽減することもでき、公平な評価結果となることが期待されます。
また、360度評価を実施すると、課題や成果が複数人の視点による多面的な形で明らかになります。社員の自己認識の改善が期待でき、課題解決や能力開発につなげやすくなるでしょう。さらに、お互いが評価し合うため会話が増え、社内のコミュニケーションが活発化するケースもあるでしょう。
このように、360度評価は人事評価の手法のひとつであるだけでなく、人材育成や組織の活性化といった効果も期待できます。
360度評価の導入が進む背景
360度評価は、以下のような背景の下で導入が進んでいます。
- 人事制度の変化
- 働き方の多様化
多くの社員が同じように昇格・昇進する従来の年功序列の制度の下では、年齢や勤続年数が重要な要素であり、人事評価の持つ意味はそれほど大きくはなかったともいえます。しかし、雇用慣行の変化に伴い増加している成果主義の下では、人事評価の重要性が高くなります。そのため、より精度の高い人事評価の実現が期待できる360度評価が注目されているのです。
また、働き方改革によりフレックス勤務やリモートワークが増加したことも、360度評価導入が進む背景です。フレックス勤務やリモートワークでは、一人ひとりの成果や働く姿勢を、管理職が把握できないケースも少なくありません。360度評価により各社員に関わるさまざまな関係者からの評価を得ることで、働き方にかかわらず、より実態に即した評価を行うことが可能になります。
360度評価の評価項目
ここでは、360度評価における評価項目を2つのケースについて解説します。評価項目をあらかじめ明確にし、スムーズな360度評価を実現しましょう。
部下または同僚を評価する場合
上司から部下、または同僚から同僚への評価を実施する際の評価項目には、以下のものがあります。
- 主体性
- 業務遂行力
- 解決力
- 協調性
部下や同僚を評価する際は、業務やチームの課題を自分の問題としてとらえ行動する「主体性」や、業務プロセスを理解し、責任をもって最後までやり遂げる「業務遂行力」が評価されます。
また、不測の事態やトラブルの原因を特定し、適切な解決策を実行する「解決力」や、円滑なコミュニケーションをとりながら共通の目的や目標に向け共同作業ができる「協調性」も、評価のポイントです。
上司を評価する場合
部下が上司を評価する際の評価項目は、以下のとおりです。
- リーダーシップ
- マネジメント力
- 判断力
- 人材育成力
- 目標達成志向
部下が上司を評価する場合は、組織全体の目標を部下に伝え、率先して行動するリーダーシップやマネジメント力が評価されます。責任をもって迅速かつ的確に意思決定をする「判断力」も、管理職の場合は特に重要です。
また、部下の能力や性格、適性を把握し、計画的に後継者を育てる「人材育成力」や、目標達成に向けて努力を惜しまない「目標達成志向」も評価の対象となります。
360度評価を実施する手順
360度評価は、以下の手順で実施することで、より効果的なものとなります。
- 現状の把握と導入目的の明確化
- 導入範囲と評価方法の決定
- 評価項目の設定
- 実施の周知
- 運用
- フィードバック
まずは、現状を把握し導入目的を明確にすることが重要です。目的が明確になったら、導入範囲と評価方法を決定します。評価者ごとに評価の観点が異なることのないよう、評価項目もしっかりと設定しておきましょう。
導入前には、360度評価を実施する旨を社員に周知します。目的や実施方法をあらかじめ十分に伝えることで、トラブルなく導入を進められるでしょう。
運用を開始した後は、評価項目の有効性の分析と、評価対象者に対する評価のフィードバックを定期的に実施します。フィードバックでは、対象者に評価内容をしっかり説明することで、評価に関する本人の理解を深められます。
360度評価のメリット
360度評価では、複数人の評価による精度の高い評価が実現でき、以下のようなメリットが考えられます。
- 対象者が納得のいく評価を実施できる
- 対象者が自分自身の課題に気づける
- 人間関係のトラブルを早期に発見できる
それぞれを詳しく解説します。
対象者が納得のいく評価を実施できる
360度評価では、1人の評価者だけでなく複数人による評価がなされることで、客観性と公平性が生まれ、評価に対する対象者の納得感が高まります。特に、上司と接する時間が少ない社員の場合、上司以外からの評価も加味されていることで、より正当な評価を受けられていると感じることができるでしょう。また、仮にネガティブな評価がなされた場合でも、1人による評価は受け入れづらくとも、複数人から同じことを指摘されている場合には耳を傾けやすくなります。
納得して評価を受け止められると、業務に対するモチベーションも向上するでしょう。さらに、モチベーションが向上することで、社員自身による積極的なスキルアップも期待できます。
対象者が自分自身の課題に気づける
評価対象者が自分自身の課題に気づける点も、360度評価のメリットです。複数人からの評価を受けることで、自己評価と他者評価のギャップを知ることができます。自分自身が抱える課題を自覚し、主体的に改善に取り組めるようになるでしょう。
同時に、360度評価により自分自身が気づいていなかった強みを知ることができる場合もあります。そのようなときは、能力についての新たな気づきをキャリア形成につなげていくこともできるでしょう。
人間関係のトラブルを早期に発見できる
360度評価は、多くの社員が関わる形で実施されるものであり、その中の人間関係が評価に影響を及ぼす場合があります。
たとえば、チームの中で1人だけ著しく悪い評価が付けられたときは、その社員自身に問題があるとは限らず、いじめやハラスメントなど何らかのトラブルが発生している可能性も考えられるでしょう。また、そもそもコミュニケーションがとれていない部署では、360度評価がうまく機能しないケースもあります。
このように、360度評価が円滑に進まないときは、社内の人間関係にトラブルが潜んでいることも少なくありません。360度評価を通してトラブルの早期発見ができれば、問題の速やかな解決が期待できます。
360度評価のデメリット
360度評価にはメリットがある一方、以下のようなデメリットもあります。
- 関係性が評価に影響する可能性がある
- 関係性に影響が及ぶ可能性がある
- 人員や工数がかかる
- 効果が得られるまで時間がかかる
それぞれをしっかりと確認し、トラブルのない導入を目指しましょう。
関係性が評価に影響する可能性がある
360度評価のデメリットの1つが、社員の人間関係が評価に影響する可能性がある点です。社員がお互いに評価し合う360度評価では、日ごろの人間関係やそれぞれの役職、立場によって評価が変わる可能性があります。
たとえば、同期入社の社員など普段から仲が良い社員同士では、お互いに高評価を付け合うこともあるでしょう。悪く思われたくない、といった理由で、甘い評価を付けることもあるかもしれません。反対に、ライバルや不仲といった間柄の場合、低い評価を付けるケースも考えられます。
このようなデメリットを解消するためには、評価項目を明確にし、評価者と対象者の関係性が反映されにくい体制を作ることや、適正な運用が行われるように360度評価導入の目的を社内全体で共有することが重要です。
関係性に影響が及ぶ可能性がある
360度評価は、複数の立場からお互いを評価し合うものであり、評価内容が今後の関係性に影響を及ぼす可能性があります。
360度評価では、低い評価を付けたり課題を提示することもあるでしょう。社員の成長や企業の生産性向上などを目指すためには、ときに厳しい評価も必要です。しかし、360度評価の目的が社内で十分に共有されていない場合、対象者は評価者から単に自分の能力を否定されたと感じ、評価者との今後の関係性に影響が及ぶおそれがあります。
また、360度評価では、上司も部下から評価を受ける立場となります。そのため、部下から低い評価を受けることを避けるため、厳しい指導が必要な場面でも指導をしなくなったり甘い指導にとどまってしまうといったおそれもあります。
評価実施後の人間関係や業務遂行を円滑に保つには、360度評価実施の目的を再確認するとともに、評価のフィードバックを丁寧に実施し、フォローアップを行うことが大切です。ときには、匿名での評価とする、評価項目を見直すといった対応も必要となるでしょう。
人員や工数がかかる
360度評価は、お互いに評価をし合うものであるため、上司が部下を評価するのみの制度と比べ、評価を行う社員数と工数が増し、社員の業務量が増えることとなります。
また、スムーズに360度評価を実施するには、評価項目の設定や導入目的の周知、正しい評価を実施するための社内研修など、さまざまな準備が必要です。水平的評価や垂直的評価と比較し、実施の手間が増えることは留意するとよいでしょう。
このように、人員や工数を必要とする360度評価は、場合によっては各社員の本業に影響が及ぶ可能性があります。それぞれの社員が360度評価に前向きに取り組むためには、導入の目的やメリットを事前に明確にし、周知することが重要です。
効果が得られるまで時間がかかる
上述のとおり、360度評価には、導入により社内の人間関係に影響が生じたり、社員の業務負担が増えたりするといったデメリットがあります。失敗を防ぎスムーズな運用を軌道に乗せ、さらに評価の最適な実施や人材育成といった効果を得るには、年単位での時間を要します。導入による明確な効果をすぐに実感することが難しく、実施を継続し定着させていくことには難しさがありますが、360度評価を有効なものにするには、長い目で施策を実施していくことが肝心です。
360度評価を導入する際のポイント
最後に、360度評価を導入する際のポイントを解説します。
- 目的と評価項目を明確化し周知する
- 人事評価の対象者全員をなるべく評価の対象とする
- 対象者ごとに適切な評価者を設定する
- 評価対象者にフィードバックを実施する
- 評価者向けの研修を実施する
それぞれの内容を十分に確認し、より効果的な実施を目指しましょう。
目的と評価項目を明確化し周知する
360度評価を導入する際は、評価項目を明確化し周知することが大切です。評価項目や基準が統一されていないと、評価者によって評価の仕方が異なったり主観が入ったりする可能性が生じます。公平で客観的な評価を実施するために、評価項目をあらかじめ明文化し、誰でも確認できるように整えておく必要があるといえます。
また、360度評価は何のために実施し、評価結果は何に用いるのかについても、明確化し周知しておくべきです。目的についての説明がない状態では、社員の混乱や不安を招きかねません。制度に対する社員の理解の下で実施し、効果を十分に得られるよう、丁寧に説明することが望ましいといえます。
人事評価の対象者全員をなるべく評価の対象とする
360度評価は、客観性と公平性のある評価を実施できることがメリットのひとつです。対象者を一部の社員に限定してしまっては、そのメリットが薄れてしまいます。仮に管理職のみを対象とする場合も、対象となる管理職とそうでない管理職が生じるといったことのない制度設計となるよう留意するとよいでしょう。
対象者ごとに適切な評価者を設定する
360度評価では、対象者ごとに複数の評価者を選ぶこととなりますが、効果をより高めるには、対象者を適切に評価できる評価者を選ぶ必要があります。
たとえば、同じ部署やプロジェクトに属している、普段から一緒に仕事をしている、など、仕事上の関わりがあることは、評価者を選ぶ上で重要な点となります。また、特定のポジションや年齢に偏ると、評価の多面性が低減してしまいます。評価者の属性のバランスを考慮して選定できるとよいでしょう。
評価対象者にフィードバックを実施する
360度評価を効果的なものにするには、評価を付けて終わりではなく、評価を分析し、評価対象者にフィードバックすることが重要です。
適切なフィードバックを受けることで、それぞれの社員が評価への理解を深め、結果を前向きに業務に活かしていくことができます。課題についても自覚を持って自発的に改善に取り組むことが期待できるでしょう。フィードバックが不十分であれば、制度自体に意味があるのかという疑問も生まれ、社員の理解や協力を得ることが難しくなる可能性もあります。
フィードバックを実施する際は、良い効果につながるよう、適切なタイミング・場所で行う、課題を伝える際は具体的な改善策も提示する、問題点や課題ばかりではなく良い点も併せて伝える、といったことが肝心です。
評価者向けの研修を実施する
360度評価を有効なものとするには、各評価者が目的や効果を理解すること、すべての評価者が主観に拠らず同じ基準で評価できるようにすることが重要です。そのためには、評価者に対して研修を実施し、適切な評価ができるスキルと知識を身につけてもらう必要があります。
また、研修を通じて360度評価のデメリットについても理解してもらうことで、悪影響が生じるのを避ける形で実施することにもつなげられるでしょう。
まとめ
360度評価とは、社員に関係するさまざまな立場の人が評価者となることで、公平かつ客観的な評価を目指す人事評価の手法です。人事制度や働き方の変化により、近年は360度評価を採用する企業が増えています。
360度評価のメリットとして、納得がいく評価を得やすい点や社員が自分自身で課題に気づけるといった点があります。一方、実施にあたり人員や工数が必要な点や、社員の関係性と評価の間で相互に影響が及ぶ可能性がある点には注意が必要です。
360度評価を導入する際は、導入目的の周知や評価項目の明確化、評価者研修などを実施するとよいでしょう。

この記事を担当した人
PeopleX コンテンツグループ
人事・労務・採用・人材開発・評価・エンプロイーサクセス等についての用語をわかりやすく解説いたします。
これまでに出版レーベル「PeopleX Book」の立ち上げ、書籍『エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針』の企画・編集、PeopleX発信のホワイトペーパーの企画・編集などを担当しました。
- 株式会社PeopleXについて
- エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発・運営をはじめとした、新しい時代に適合したHR事業を幅広く展開する総合HRカンパニーです。