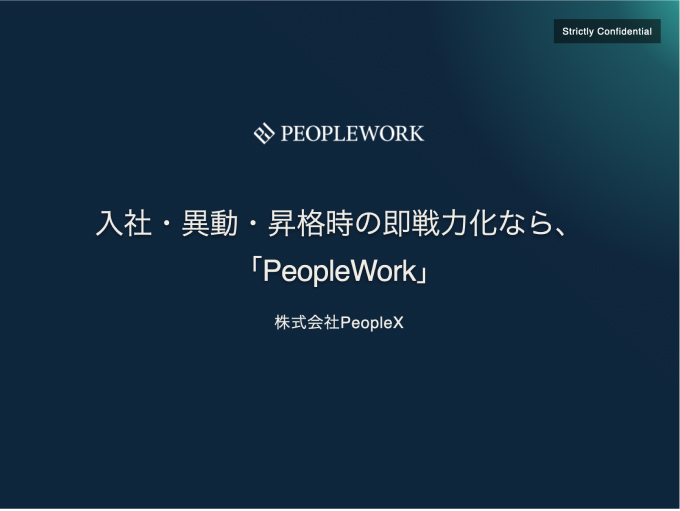エンプロイーサクセス
2024.08.08
離職率を下げる方法とは? 原因や対策、企業の人材流出防止の取り組み事例を紹介
- #人事労務
- #離職率低減

社員の離職率が高いと、企業の成長や安定に大きな影響を及ぼしますし、残された社員のエンゲージメントも低下するおそれがあります。そこで本記事では、離職の原因と、離職率を下げるための具体的な方法を解説します。
加えて、企業が取り組むべき対策や成功事例も紹介しています。たとえば、柔軟な働き方の導入やワークライフバランスの改善、社員のキャリア成長支援など、多くの企業が実施している実際の取り組みを通じて、どのように人材流出を防いでいるのかを、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも離職率とは
離職率とは、ある時点で雇用されていた社員のうち一定期間内に離職した社員の割合を示す指標です。ここでの「一定期間」は、1年間で設定することが一般的ですが、離職率を算出する目的に合わせて、たとえば3年間というように自由に設定することが可能です。離職率は企業における社員の定着率を評価する指標となり、離職率の高い職場は環境や労働条件の改善が必要であると考えられます。
離職率の計算方法
離職率を計算する際は、期間内の離職者数を期間の初めの社員数で割り、100を掛けてパーセンテージで表します。
たとえば、入社後1年時点での新卒社員の離職率を計算してみます。新卒採用が20人、そのうち1年で2人が退職したという場合、
離職率=離職した新卒社員数÷新卒社員の総数×100
=2÷20×100
=0.1×100
=10%
となります。
退職率との違い
「離職率」と混同されやすい言葉が「退職率」です。どちらも会社を辞める社員の割合を表すために使われるものですが、退職率は、「自己都合」や「定年退職」などを理由に会社を辞めた社員の年齢ごとの割合を指します。主に、将来の退職の割合を予測するために用いられます。
一方で離職率は、自己都合か会社都合か、解雇か、契約満了による退職かなど、理由を問わず、一定の期間内に会社を離れた社員の割合です。それぞれ異なる観点で企業全体の社員の流動を把握する指標であるといえます。
定着率との違い
「定着率」とは、入社した社員が一定期間後にどのくらい自社で働き続けているかを示す指標です。定着率が高いほど、社員の離職が少なく、組織の体制が安定的であると判断できます。
たとえば、入社後1年時点で、新卒採用20人のうち18人が退職残っていたという場合、新卒社員の定着率は以下のとおりとなります。
定着率=残っている新卒社員数÷新卒社員の総数×100
=18÷20×100
=90%
上で見た離職率と照らし合わせるとわかるように、離職率は、一定期間後にどのくらい離職したかを示すものであり、定着率と離職率は対になる指標です。企業としては、離職率が低く、定着率の高い状態が理想的であると言えます。
日本における離職率の現状
離職率の平均
厚生労働省の「令和5年『雇用動向調査』の調査結果」によると、2023年(令和5年)1年間の日本の全産業平均の離職率は約15.4%でした。性別に見ると、男性は13.8%、女性は17.3%、就業形態別に見ると、一般労働者は12.1%、パートタイム労働者は23.8%となっており、前年と比べると、男女とも一般労働者・パートタイム労働者のいずれでも上昇しています。
産業別に見ると、以下のとおりです(本数値は一般労働者、括弧内はパートタイム労働者の離職率を示します)。
離職率が高い上位3産業
1.生活関連サービス業,娯楽業:20.8%(36.9%)
2.サービス業(他に分類されないもの):19.3%(32.7%)
3.宿泊業,飲食サービス業:18.2%(31.9%)
離職率が低い上位3産業
1.複合サービス事業:6.8%(12.6%)
2.鉱業,採石業,砂利採取業:9.3%(6.1%)
3.製造業:8.7%(16.3%)
離職率の高い業界は、接客・サービス関連の業界が多く、給与水準の低さや人間関係のストレス、長時間労働などが影響していると考えられます。
一方で、離職率の低い業界はインフラ業や製造業が多く、これらの業種では、長期的なキャリア形成のしやすさや専門性が求められるといった要因が離職率を押し下げていると考えられます。
参照:厚生労働省 雇用動向調査
新卒社員の離職率
2024年10月に厚生労働省が公表した「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」によると、就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者が38.4%、新規大卒就職者が34.9%となりました。過去10年間を見ると概ね横ばいではあるものの、直近3年間は緩やかに上昇傾向にあります。
参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」
中途社員の離職率
一般的な傾向として、中途採用者の離職率は高いとされ、2年以内での離職率が30%を超えるとの指摘もあります。
これにはいくつかの理由が考えられます。その一つとして、入社前後のギャップが挙げられます。中途採用者は、前職での経験があり、働き方やコミュニケーションスタイルの違いから悩みやストレスを抱えてしまうことも考えられます。会社の方針や仕事内容、評価についても、前職での経験や比較も踏まえながら期待や展望を持つことが多いと言えますが、実際に入社したらイメージと違っていたといった場合にも、離職の可能性が高まると言えます。
また、中途採用者は、即戦力として期待されることが多く、業務に関する説明をはじめとした入社後のフォローが不十分となるケースもあります。このような場合も、離職率を高める一因となります。
離職率を下げるメリット
離職率を下げることには、以下の4つのようなメリットがあります。
- 採用・教育コストの削減
- 既存社員のモチベーション向上
- 人材確保の競争力強化
- 企業イメージの向上
詳しく見ていきましょう。
採用・教育コストの削減
新たな社員を採用するためには、求人広告費や採用活動の費用がかかります。また、 新入社員をトレーニングし、業務に慣れさせるための時間と費用が必要です。離職率を下げることで、これらのコストを削減することができます。
既存社員のモチベーション向上
経験豊富な社員の退職に伴い、業務が停滞し、生産性が低下するリスクがあります。そのしわ寄せは既存社員にのしかかります。既存社員がしわ寄せに過度な不満を持つと、離職を選ぶリスクもあります。連鎖的な離職を阻止するためにも、離職率を下げることが効果的でしょう。
人材確保の競争力強化
日本の少子高齢化により、人材の確保が難しくなってきています。また、副業やリモートワークの普及により、転職のハードルが下がったことで、人材の流出が加速しています。その中で、離職率を下げることで、企業は優秀な人材を長期間維持でき、安定した組織運営が可能になります。
企業イメージの向上
離職率が高いと企業の評判が悪くなり、優秀な人材を引き付けにくくなります。とくに、インターネットを通じて離職率が高い企業が容易に特定される現代において、企業イメージを守るためには離職率の低減が重要です。離職率を下げることで、外部からの評価が向上し、企業の魅力を高めることができます。
離職率が高まる原因
離職の原因は多岐にわたりますが、主なものは次のとおりです。
給与や福利厚生の不満
他社と比較して給与が低かったり、過度の業務負担や長時間労働に見合った給与が支払われていないと社員が感じた場合、仕事へのモチベーションが低下します。また、福利厚生が不十分だと感じた場合も、自分の生活や将来に対する保障を求めて転職を考えるようになります。
キャリアアップや成長の機会の不足
キャリアアップの道筋が不透明であったり、昇進やスキル向上の機会が与えられない場合、社員は自身の成長を実感できず、将来に対する不安や焦りが募ります。昇進等が見込めない、または業務に対して十分なフィードバックや評価がない状況では、社員のモチベーションが低下し、他社でのキャリア形成を目指して転職を決意する可能性が高まります。また、企業の評価制度が不公正であると感じると、離職のリスクはさらに高まります。
職場環境の問題
職場での人間関係が悪かったり、職場文化が合わないと感じたりすることも大きなストレス源となり、離職を引き起こす原因です。上司や同僚とのコミュニケーション不足も業務に悪影響を及ぼし、モチベーション低下を招きます。また、ハラスメントが存在する場合も、職場の雰囲気を悪化させ、社員の離職を加速させます。
ワークライフバランスの欠如
長時間労働や過度な休日出勤が常態化している職場では、プライベートとのバランスを取ることが難しくなり、とくに家庭を持つ社員にとっては不満の原因となります。たとえ給与が高くても、ワークライフバランスが取れない場合、精神的にも身体的にも負担が大きくなり、結果的に離職につながります。
仕事内容の不満
仕事に対するやりがいや面白みを感じられない場合、社員はやりがいを求めて転職を決意することがあります。とくに本人が期待していた業務内容と実際に任された業務内容に大きなギャップがある場合、その不満が蓄積し離職につながります。また、自分の仕事が会社の成長に貢献している実感が持てなかたり、お手本になる上司や先輩がいない場合も離職を促してしまいます。
職場の安定性や将来性への不安
会社の業績悪化や将来の見通しの不透明さは大きな不安要素となります。これにより未来のビジョンを描けず、転職を選ぶ動機が強まります。とくに、企業の経営状態が不安定だと感じた社員は、早期に転職先を探し始めることが多くあります。
これらの原因を理解し改善することで、離職率を下げることができます。
しかしながら、離職率が高いことは、一概に悪いことばかりとは限りません。たとえば、経験を身につけた後は次のステップに進むことを推奨する文化を持つ企業もあります。また、新陳代謝により新しいアイデアや視点が企業にもたらされ、組織の活性化やイノベーションの推進に寄与することもあります。
そのため、ポジティブな退職と防げたはずの退職を切り分けて考え、後者を防ぐ手立てを考えるとよいでしょう。
離職する可能性が高い社員の特徴
離職する可能性が高い社員には、以下のような特徴があります。
業務に対するモチベーションが低い
仕事に対して興味や情熱を持てず、やる気が低下している社員です。ミスが増えたり、仕事を他人に押し付けるなどして、仕事効率が落ちていることが多いです。
ストレスを感じている
業務量が多すぎる、職場の人間関係が悪いなど、ストレスを多く感じている社員です。パワハラ、セクハラなどハラスメントによる影響がある場合もあるでしょう。また、社内でのコミュニケーションが希薄になる傾向も見られます。
キャリアの方向性が不明確
自分のキャリアプランが明確でなく、将来に不安を感じている社員です。結婚や出産、介護など、ライフステージが変化し、働き方に影響が出ていることもあります。
これらの兆候が見えたら、早めに対策する必要があると言えるでしょう。
離職率を減らす施策
社員の離職を防止するためには、以下のような施策が考えられます。
- 退職理由の特定
- 採用活動の見直し
- マネジメントスキルの向上
- 研修制度の強化
- 給与、待遇の見直し
- 労働時間の見直し
- 柔軟な働き方の実現
- 良好な職場環境の構築
- 経営方針やビジョンの共有
それぞれ詳しく見ていきましょう。
退職理由の特定
退職していく社員に対してヒアリングを行い、自社の問題点を明らかにします。とくに退職手続後にヒアリングを実施することで本音を引き出せます。
採用活動の見直し
求職者への情報提供を活発化し、なるべく入社後のイメージを明確にもった状態で入社してもらうようにしましょう。入社後のフォロー面談も重要です。早期にミスマッチを把握することで、離職が防げる可能性があります。
マネジメントスキルの向上
管理職に対して定期的にマネジメント研修を実施し、上司の部下に対する適切な対応を促進します。ハラスメント研修などを取り入れることも推奨されます。
研修制度の強化
研修制度を整え、社員のスキルアップを支援することが離職防止につながります。定期的な面談を行い、社員のキャリアプランや不満を把握し、適切な人材配置を行うことも重要です。一人ひとりに適した支援と人材配置を実現することで、会社への貢献意欲を高めることができるでしょう。
評価制度の見直し
社員に不公正な評価制度だと感じられることは、離職につながる一因となります。適切な評価制度を確立し、社員の成果を正当に評価することでモチベーションを向上させることが求められます。
給与、待遇の見直し
給与や福利厚生は社員の離職理由に直結する重要な要素です。これらを改善することは離職率低下の近道と言えます。同業他社と比較して低い労働条件となっている場合は、適切な内容への改善が必要でしょう。住宅手当や育児・介護支援の制度を整えるなど、社員の安心感を高めることも有効です。また、雇用形態によって待遇が異なる場合、不合理な差であってはならないのはもちろんですが、納得感が得られるものであることも大切です。企業が社員を大切にし、正しく評価している姿勢が離職率を抑えることにつながります。
労働時間の見直し
長時間労働や過度な休日出勤が続く職場では、社員の精神的および身体的な負担が増し、離職率が高くなる原因となります。これを改善するためには、業務の効率化や業務の再編成、ノー残業デーの導入などが効果的です。業務負担の適正化を図ることで、社員の健康を守り、長期的な定着を促進します。さらに、定期的に社員の労働環境を評価し、必要な改善を行うことが重要です。
柔軟な働き方の実現
柔軟で多様な働き方のできる労働環境を整えます。職種によっては実現できないこともありますが、テレワークやフレックス制、時短勤務などの制度があることで、育児や介護による離職を減らすことにつながるケースもあります。
良好な職場環境の構築
職場環境の改善は、社員の定着率向上に直結します。たとえば、社員間でのコミュニケーションの活性化やハラスメント対策の徹底、メンタルヘルス支援の強化などが挙げられます。また、快適な業務空間の提供や疲労回復支援施設の設置など、ハード面での施策も効果的です。これらの施策により、社員が安心して働ける環境が整い、離職率の低下が期待できます。
経営方針やビジョンの共有
企業の経営方針やビジョンを社員と共有することで、組織への帰属意識やモチベーションが向上します。具体的には、定期的な全体ミーティングや社内報を通じて、企業の方向性や目標を明確に伝えることが効果的です。また、社員からのフィードバックを積極的に受け入れ、双方向のコミュニケーションを促進することも重要です。これにより、社員は自らの役割や貢献を実感しやすくなり、離職率の低下につながります。
上で見た社内の活性化や経営方針・ビジョンの共有といった施策をより効果的に実施するには、双方向コミュニケーションも実現する「PeopleWork」の「社内報・賞賛」機能が役立ちます。「PeopleWork」にご興味をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードして詳細をご確認ください。
離職率低下のための企業の取り組み例
社員の働きやすい環境を整え、ワークライフバランスを向上させることで、優秀な人材の流出を防ぎ、企業の競争力を維持するため、様々な取り組みが行われています。ここでは、実際にいくつかの企業の施策を紹介します。
第一生命保険株式会社
「両立支援制度」の充実と柔軟な働き方の推進を目標に掲げ、男性社員の育児休業取得率を100%に引き上げる取り組みを行っています。また、育児サービス経費補助や不妊治療に使用できる休暇制度の整備、テレワークの活用なども進めています。
参照:第一生命
ヤフー株式会社
土曜日が祝日の場合に前日の金曜日を休暇にする「金曜振休制度」を導入しています。また、10年勤続した社員に対して2、3ヶ月の長期休暇の取得を認めています。これにより、社員のワークライフバランスの向上を目指しています。
参照:ヤフー株式会社
エーザイ株式会社
シェアオフィスやワーケーションを活用し、働き方の多様化を推進。多様な社員が様々な環境下で生産性高く、健康的に、自分らしく仕事をできる環境の整備に取り組んでいます。たとえば、部下の育休取得や短時間勤務においても、滞りなく業務を進めるための施策を取り入れています。
参照:エーザイ株式会社
まとめ
離職率の低下は、企業の生産性向上やコスト削減、社員の働きやすさの向上につながる重要な課題です。給与や待遇の見直し、キャリア開発支援、ワークライフバランスの推進、職場環境の改善など、様々な取り組みを総合的に行うことで、離職率を低下させることができます。

この記事を担当した人
PeopleX コンテンツグループ
人事・労務・採用・人材開発・評価・エンプロイーサクセス等についての用語をわかりやすく解説いたします。
これまでに出版レーベル「PeopleX Book」の立ち上げ、書籍『エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針』の企画・編集、PeopleX発信のホワイトペーパーの企画・編集などを担当しました。
- 株式会社PeopleXについて
- エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発・運営をはじめとした、新しい時代に適合したHR事業を幅広く展開する総合HRカンパニーです。