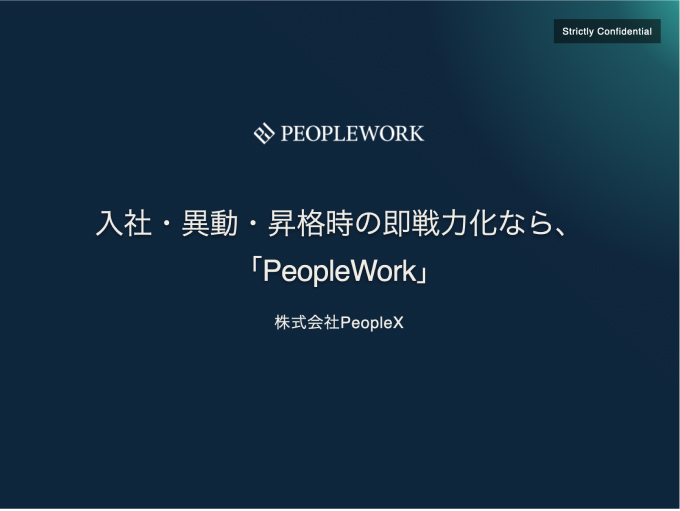人材開発・教育
2025.04.14
学習性無力感とは? 意味や原因、企業が採るべき対策を解説
- #人材育成
- #職場環境

業務に対して社員の自主性や積極性が感じられないことを、本人のやる気のせいにしてはいないでしょうか。しかし、本人に原因があるのではなく、学習性無力感という状態に陥っている可能性も考えられます。
社員が学習性無力感に陥った場合には、やる気をなくし指示待ちの姿勢が強くなります。この記事では、学習性無力感とは何かを確認し、学習性無力感が仕事に及ぼす影響や、陥りやすい人の特徴、企業として採るべき対策について解説します。
学習性無力感とは|意味と具体例
学習性無力感とは、「何をやっても無駄である」と学習した結果、問題を解決しようという気力や意欲自体が失われることです。人間だけでなく、動物でも同じような事象が確認されています。まずは学習性無力感の概要と、ビジネスにおける学習性無力感の具体例を整理してみましょう。
学習性無力感とは「抵抗を諦める」状態になること
学習性無力感とは、抵抗や回避ができないストレスにさらされ続けるうち、それらからの回避を諦める状態になることです。1967年に米国の心理学者であるマーチン・セリグマン博士が、動物実験によって確認し、発表しました。
実験では、犬を2つのグループに分け、以下のような条件下に置きました。
- Aグループ:電流を流されるが、ボタンを押せば電流が止まる
- Bグループ:電流を流され、ボタンを押しても電流が流れ続ける
その後、「飛び越えられる低い柵で囲われたエリア」に入れ、エリア内で電流を流したところ、Aグループの犬は柵を飛び越え電気ショックを回避する行動をとりましたが、Bグループの犬は柵を飛び越えようとせず、ただ電流に耐えていたそうです。
この実験から、セリグマン博士は「Bグループは何をしようと電流から逃れられない環境に置かれたために、回避行動をとることすらしなくなった」と結論づけました。また人間についても、大きな音を聞かせるというストレスで同様の実験を行い、犬と同様に回避行動を諦める傾向があることを確認しています。
学習性無力感は、年齢を問わず陥る可能性があります。子どもであれば、努力して勉強しても授業についていけない、習い事を頑張っても上達しないといったことで学習性無力感にとらわれることがあります。高齢期においては、退職や心身の衰えを主な原因として、学習性無力感に陥ることがありえます。
ビジネスにおける学習性無力感の具体例
ビジネスシーンでも学習性無力感に陥ることが考えられ、具体例としては、たとえば以下のような事象が挙げられます。
- ノルマを達成できないことが続き、ノルマ達成への意欲がなくなる
- 改善提案をしても受け入れてもらえないことが続き、提案する意欲がなくなる
- 激しい叱責を受け続けるうちに、抵抗する意欲がなくなる
これらに共通するのは、「最初はやる気があったが、抵抗してもストレス状態から脱却できない状態が続いた結果、抵抗する意欲がなくなる」という点です。最初からやる気がないわけではありません。「力を注いでも成果が出ない」「抵抗しても状況が変わらない」といった状況に置かれ、やる気を失い、無気力になるのです。
学習性無力感が仕事にもたらす影響
学習性無力感は、仕事に以下のような影響をもたらします。
- 仕事へのモチベーションが低下する
- イノベーション創出の機会を失う
- 職場にネガティブな雰囲気が蔓延する
本人だけでなく周囲の社員や会社全体にも悪影響を及ぼすことにも注意を要します。それぞれ詳しく見ていきましょう。
仕事へのモチベーションが低下する
「努力してもうまくいかない」「提案しても聞き入れてもらえない」という状況が続くと、自信を失い、仕事へのモチベーションが低下します。いったん学習性無力感の状態に陥ると、積極的に動けば解決できるという状況であっても行動する気力は起きません。その結果、いわゆる指示待ちの姿勢になります。
指示待ちの状態では、業務の生産性が下がるでしょう。結果として、所属するチームや会社全体の生産性の低下にもつながります。
イノベーション創出の機会を失う
提案する意欲を社員が失くした結果、社内で新しいアイデアが出てこなくなり、イノベーションを創出する機会が失われます。前例がないことへの挑戦や改革の実行は、企業としての競争力を高める上で必須ですが、そういった機会がなくなることで、変化する社会経済情勢に対応できなくなるリスクを生じさせてしまいます。
職場にネガティブな雰囲気が蔓延する
ひとりの社員が学習性無力感に陥ると、周囲の社員にもネガティブな様子が伝わり、部署やチーム全体が学習性無力感に近い状態になります。「何をしても無駄」という意識は、会議での発言のなさや愚痴といったネガティブな言動の形をとって他の社員に伝わり、後ろ向きな姿勢や考え方が広がっていってしまうのです。
たとえば、やる気を持って入社した社員でも、「頑張っても意味がない」といった先輩社員の愚痴を聞けば、モチベーションの維持が困難になるでしょう。何かにつまずいたときに、先輩が言ったとおりだと独り合点してしまい、先輩社員のネガティブな言動がなかった場合と比べてより早く学習性無力感に陥ってしまう危険があります。
学習性無力感の原因や陥りやすい人の特徴
同じような失敗やストレスにさらされても、学習性無力感に陥るかどうかは人によって異なります。特に以下のような人は、学習性無力感に陥りやすいと言われています。
- 自己肯定感が低い完璧主義の人
- 成功体験が少ない人
- ストレスの多い環境に置かれている人
それぞれ詳しく見てみましょう。
自己肯定感が低い完璧主義の人
自己肯定感が低い人は、小さな失敗でも「自分が悪い」と感じやすい傾向があります。また、完璧を目指すタイプの人は、うまくいった部分よりもうまくいっていない部分にばかり意識を向けてしまいがちです。中には、ほとんどの人が失敗と思わないようなことでも、失敗と捉えて過度に落ち込んだり反省したりする人もいます。
このような人は、失敗したという経験や意識を必要以上に強く持ってしまうため、学習性無力感に陥りやすくなります。
成功体験が少ない人
成功体験が少ない人は「努力すれば成果が出る」という認識に乏しいため、自信を喪失しがちです。比較的少ない回数の失敗でも「やはり今回もだめだった」という結論を出しやすく、学習性無力感に陥りやすいでしょう。
成功体験が少ない人は、困難に直面した際の適切な対処方法を知らないというケースもあります。「誰かに相談する」「問い合わせる」など少しの行動で解決できることでも、実行に移せず、成功体験を積めずに学習性無力感を強めるリスクがあります。
ストレスの多い環境に置かれている人
職場でストレスが多い環境にある人は、抵抗や回避行動が成功しにくく、学習性無力感に陥りやすいと言えます。具体的には、以下のような職場環境が挙げられます。
- 職場でモラハラ、パワハラを受けている
- 仕事に対する適切なフィードバックが受けられない
- 大きな失敗や人間関係の問題で精神的に不安定な状態が続いている
たとえば大きな失敗があっても、周囲のフォローが適切に行われていれば、ひとりで抱え込むことはありません。問題になるのは、フォロー体制がなく、精神的に不安定な状況が続く場合です。
このような状況は心身の不調や休職につながるリスクも高く、迅速な環境の改善が必要です。個人の問題として片づけず、組織として対応しましょう。
学習性無力感に陥るのを防ぐには|企業が採るべき対策
学習性無力感には個人の性格や考え方といった要因もありますが、以下のような対策によって防止することができます。
- 成功体験の積み重ねを促す
- 社内の風土の変革を図る
- ポジティブな声掛けを意識する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
成功体験の積み重ねを促す
ひとつの対策として、社員に大きな目標ではなく達成しやすい小さな目標を立てさせ、成功体験の積み重ねを促しましょう。この対策は特に、自己肯定感が低い人や成功体験が少ない人に対して有効です。
「努力すれば達成できる」というレベルよりももう一段低く、「ひとつ行動すれば達成できる」という程度の目標で構いません。まずは「自分が行動したことで達成できた」という経験を積むことで、学習性無力感からの脱却が期待できます。
社内の風土の変革を図る
「学習性無力感が会社全体に及んでいる」という場合は、社内の風土そのものを変える必要があるでしょう。たとえば、以下のような施策が考えられます。
- 社員の声を聴く体制を整え、集まった声に対して適切な対応をする
- 社員を賞賛する機会を設ける
- 後輩育成を担う社員の教育を行う
社員の声を聴く体制としては、アンケートや1on1ミーティングの実施が挙げられます。重要なのは、実施するだけで終わりとするのではなく、集まった声に対してアクションを起こすことです。聴くだけ聴いて何も会社からアクションをしないのでは、学習性無力感を強める結果になりかねません。
また、賞賛によって社内の風土を変革するためには、本人だけでなく周囲の人にも賞賛が伝わることが特に重要です。チームミーティングや社内報などを通じて賞賛の機会を頻繁に設けることで、組織全体の心理的安全性や挑戦する意欲の向上につながるでしょう。
後輩育成を担う社員の教育には、新入社員が学習性無力感に陥るのを防ぐことを期待できます。新入社員は特に、先輩社員や現場の管理職などから大きな影響を受けるため、育成担当者がネガティブな言葉を繰り返していると、会社がどれだけ制度を整えても、モチベーションの形成・維持を阻害してしまいます。育成に関わる社員が学習性無力感の特徴や防止方法を学ぶことで、新入社員に対して適切な指導ができるようになるでしょう。
なお、賞賛の機会を増やしたり、社員に後輩の育成方法を学んでもらったりする上では、「PeopleWork」の「社内報」「オンボーディング」の機能が役立ちます。「PeopleWork」にご興味をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードして詳細をご確認ください。
ポジティブな声かけを意識する
社員のモチベーション向上のため、日頃からポジティブな声かけをするよう意識することも、対策として有効です。「叱られて成長する」という考え方もありますが、基本的に人は褒められたり期待されたりすることで成長します。
ただし、過度な期待は重圧となるため、逆にストレスの原因になりかねません。社員が「自分の頑張れる範囲で達成できる」「期待に応えたい」と思えるような、適度なものになるよう注意しましょう。
また、場を和ませるつもりの愚痴や冗談でも、社歴の浅い社員には本気の言葉ともとられかねません。無用な愚痴や冗談は控え、ネガティブな言葉自体を使わずポジティブな会話をするように心がけることが重要です。
ポジティブな声かけは、すぐに結果となって表れるとは限りません。しかし、仕事に取り組む姿勢やモチベーションなど、内面的な変化を促します。少しでも前向きな変化があれば、変化を受容し賞賛する言葉を継続的にかけていきましょう。
まとめ
学習性無力感は、抵抗や回避行動が成功しない状態が長く続いたために、回避行動をとること自体を諦めるようになった状態です。職場でひとりでも学習性無力感に陥ると、本人だけでなく周囲の社員や会社全体に悪影響を及ぼしかねません。個人の問題と捉えるのではなく、会社の成長や長期的な人材育成の観点から、対策を行うことが重要です。

この記事を担当した人
PeopleX コンテンツグループ
人事・労務・採用・人材開発・評価・エンプロイーサクセス等についての用語をわかりやすく解説いたします。
これまでに出版レーベル「PeopleX Book」の立ち上げ、書籍『エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針』の企画・編集、PeopleX発信のホワイトペーパーの企画・編集などを担当しました。
- 株式会社PeopleXについて
- エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発・運営をはじめとした、新しい時代に適合したHR事業を幅広く展開する総合HRカンパニーです。