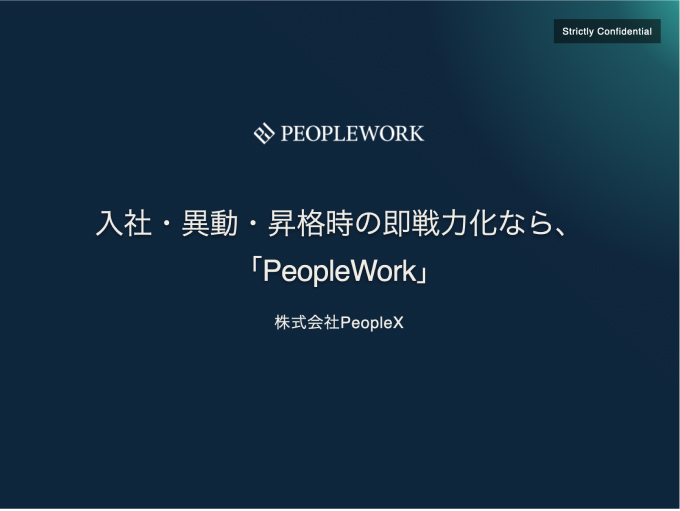人材開発・教育
2025.04.15
モチベーション管理とは? 部下のモチベーションを高めるポイントを解説
- #モチベーション
- #モチベーション上げる
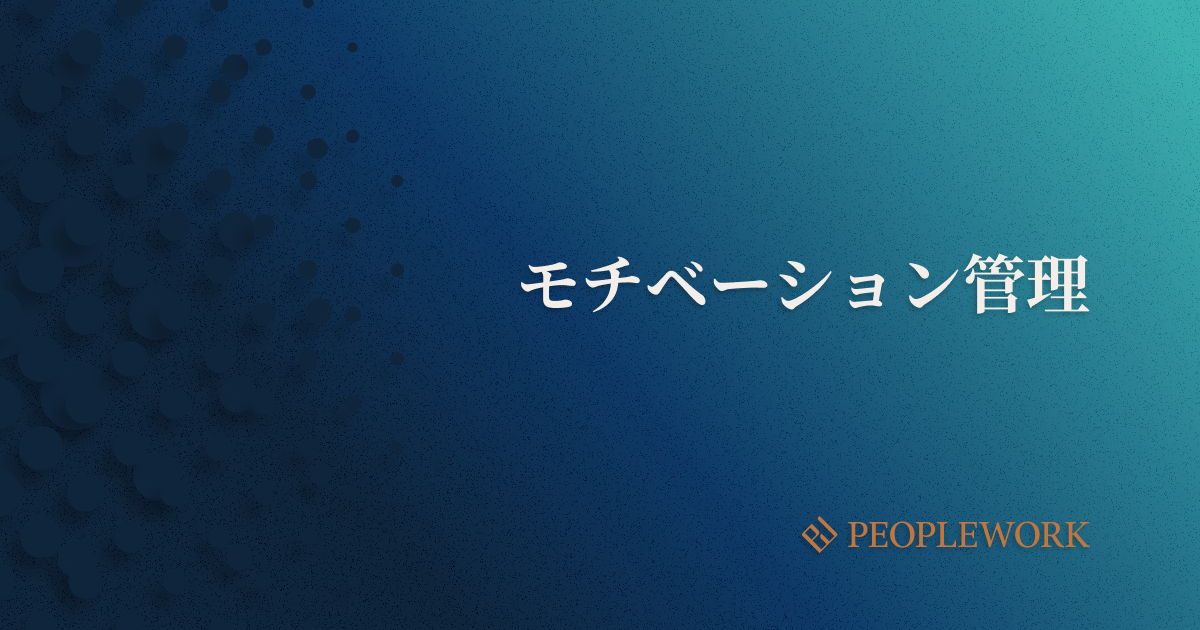
社員のモチベーションは、企業の生産性や成長に大きな影響を与えます。近年、多くの企業が「モチベーション管理」の重要性を認識し、効果的な施策を模索しています。
この記事では、モチベーション管理のメリットや、モチベーションが低下する原因、これらを踏まえた部下への接し方のポイントを解説します。
モチベーション管理とは
モチベーション管理とは、個人やチームが目標を達成するために持つ原動力や意欲を高め、維持することを指します。モチベーション管理は、企業の生産性向上や人材の定着にとって不可欠です。
社員のモチベーションが下がると業務への意欲が低下し、ミスが増えたり離職率が上昇したりして、会社全体の生産性が低下するリスクがあります。
そのため、適切な評価やフィードバック、働きがいのある環境づくりなどを通じて、社員のモチベーションを維持することが重要です。
モチベーション管理のメリット
モチベーション管理は、単に社員のやる気を高めるだけでなく、チームのパフォーマンス向上や企業の成長にもつながります。以下に、モチベーション管理を行うことのメリットを3つ紹介します。
生産性の向上
モチベーションが高い社員は、主体的に業務に取り組み、業務の効率や成果を意識するようになります。その結果、無駄な作業が減り、業務の質とスピードが向上します。また、仕事へのモチベーションが高い社員が増えることで、チームとしての結束力も高まり、組織全体の生産性が向上します。
エンゲージメントの向上
モチベーションが高い社員は、「会社のために頑張ろう」「チームのために貢献したい」という意識や、仕事への満足度・愛着を高めることができます。エンゲージメントが向上した結果、組織全体の士気や活力が向上します。
離職率の低下
社員が働きやすい環境を整え、仕事に対する満足度を高めることで、人材の流出を防ぎ離職率を下げることが可能となります。社員が定着すると、新しい人材の採用や教育コストを抑え、安定した組織運営が可能になります。さらに、長期間働く社員が増えることで、組織内にノウハウやスキルが蓄積され、企業の競争力が向上します。
モチベーションの種類|内発的動機づけと外発的動機づけ
モチベーションを適切に管理するためには、まずモチベーションそのものについて理解を深めることが重要です。モチベーションは、大きく「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」の2種類に分けられます。
内発的動機づけ
内発的動機づけとは、個人が自らの興味や価値観、達成感によって行動する動機のことを指します。たとえば、「仕事が楽しい」や「社会に貢献したい」といった理由で行動する場合がこれに該当します。このタイプのモチベーションは、持続性が高く、創造性や自発性を促進する傾向があります。
ただし、内発的動機づけは外部からの制御が困難であり、また、個人によって差が大きいといったデメリットもあります。
外発的動機づけ
外発的動機づけとは、報酬や評価、罰則など外部からの刺激によって生じる動機を指します。たとえば、「昇給やボーナスのために成果を出す」や「ミスをすると評価が下がるから気をつける」といったケースです。
外発的動機づけは即効性があり、短期間で成果を上げるのに有効ですが、時間とともに慣れが生じたり実感が低下したりしやすく、継続的なモチベーション維持には限界があることが課題となります。
このように、モチベーションには内発的動機づけと外発的動機づけがあり、それぞれの特性を理解し、バランスよく活用することが重要です。
たとえば、報酬や評価制度といった外発的な要因に加え、キャリア形成の支援や挑戦できる環境の整備など、内発的動機を引き出す仕組みも設けるというように、両側面に目配りすることが重要です。
社員一人ひとりが「自らやりたい」と感じられる状態を作ることで、個人やチームのパフォーマンス向上が期待できます。
モチベーション低下の原因
社員のモチベーションが低下する原因は、組織のさまざまな場所に潜んでいます。企業がモチベーション管理に取り組む上では、こうした原因を理解し、適切な対策を講じることが求められます。以下に、モチベーション低下の原因を6つ紹介します。
- 評価や報酬への不満
- 仕事のマンネリ化
- 人間関係の悪化
- 過度なストレスやプレッシャー
- 目標やビジョンの不明確さ
- 組織への不信感
それぞれ詳しく見ていきましょう。
評価や報酬への不満
努力や成果が正当に評価されていないと感じると、モチベーションが低下しやすくなります。とくに、昇進・昇格や昇給の機会が限られていたり、不公平に感じられる評価制度がある場合、社員は「頑張っても意味がない」と感じてしまいます。
仕事のマンネリ化
同じ業務を繰り返すだけで、新しい学びや挑戦の機会がないと、仕事への興味が薄れます。とくに、成長意欲が高い人にとっては、自分のスキルやキャリアが停滞していると感じることが、モチベーション低下の大きな要因になります。
人間関係の悪化
職場の人間関係が悪いと、働く意欲が大きく下がります。上司とのコミュニケーション不足、同僚とのトラブル、孤立感などが続くと、仕事へのモチベーションだけでなく、会社自体への愛着も薄れてしまいます。
過度なストレスやプレッシャー
過剰な業務量や厳しいノルマが課されると、プレッシャーが高まり、仕事に対する意欲が減退します。また、長時間労働が常態化している職場では、心身の疲労が蓄積し、モチベーションが低下しやすくなります。
目標やビジョンの不明確さ
自分の仕事が何のためにあるのか、会社の方向性が見えない場合、やりがいや目的意識を持ちにくくなります。とくに、経営層や上司が明確なビジョンを示さないと、社員は「この仕事にどんな意味があるのか」と疑問を抱き、モチベーションが下がる原因になります。
組織への不信感
経営陣の方針が一貫していない、会社が社員を大切にしていないなどと感じると、組織に対する信頼が揺らぎ、モチベーションが低下します。とくに、リストラや給与削減などが頻繁に行われる企業では、社員の士気が下がりやすくなります。
これらの要因が重なることで、社員のモチベーションはさらに低下し、最終的には生産性の低下や離職率の上昇につながるため、組織には早急に対処することが求められます。
モチベーションを高める接し方のポイント
社員のモチベーションを高めるためには、上司が部下に接する際、単に仕事を指示するだけでなく、部下の意見やパーソナリティを意識したコミュニケーションが重要となります。部下のモチベーションを高め維持するために、どのように接することが望ましいか、具体的な注意点を含めて以下の5つのポイントを解説します。
- 傾聴の姿勢を持つ
- 部下に裁量権を与える
- 適切なフィードバックを行う
- 公平で透明性のある評価をする
- 会社のビジョンや目的を伝える
それぞれ詳しく見ていきましょう。
傾聴の姿勢を持つ
部下の意見や考えを尊重し、しっかりと話を聴くことは、信頼関係を築く上で非常に重要です。ただ指示を出すのではなく、部下が抱えている悩みや意見に耳を傾けることで、心理的安全性が高まり、モチベーションの向上につながります。
たとえば、部下の話を途中で遮ったり、忙しさを理由に話を後回しにしたりすることは適切ではありません。部下の意見を正面から受け止めるとともに、週に一度の1on1ミーティングを設けるなどの方法をとることが求められます。
部下に裁量権を与える
すべてを細かく指示するのではなく、ある程度の裁量権を与えることで、部下の自主性が育ちます。自分で考えて判断できる環境を作ることで、仕事に対する責任感ややりがいを感じやすくなります。
たとえば、細かく指示・管理しすぎるマイクロマネジメントや、部下の提案を否定して上司の考えのみを押し付ける方法は推奨できません。しかし一方で、「好きにやって」と部下に任せきりにし、適切なフォローをしないのも適切ではありません。「どうしたらいいと思う?」といった質問を投げかけ、部下の意見を引き出す方法などが有効でしょう。
適切なフィードバックを行う
フィードバックも、モチベーションを左右する重要な要素です。成果を出したときは適切に評価し、そうでないときは改善のためのサポートを行うことが求められます。とくに、努力やプロセスを認めることで、部下は前向きな気持ちを持ちやすくなります。
たとえば、数値的な結果だけを見て否定的なコメントをしたり、ミスをした部下を感情的に叱責したりすることは逆効果です。改善を促したい場合も、問題点を指摘するだけではなく良い点をあわせて伝えることも重要です。
また、人格の否定にならないようにし、行動や結果に焦点を当てることで、部下のモチベーションを損なうことなく、前向きな改善を促せます。
公平で透明性のある評価をする
評価について不公平さを感じると、部下のモチベーションは大きく低下します。評価の基準を明確にし、誰もが納得できる形で評価を行うことが大切です。
たとえば、個人的な感情や好き嫌いで評価を変えたり、「頑張っていると感じたから」などの曖昧な基準で評価することは適切ではありません。事前に具体的な評価基準を設けて共有するとともに、昇進・昇格や昇給の理由を明確に説明し、納得感を持ってもらうことが求められます。また、定期的なフィードバックを行い、「何を改善すれば評価が上がるのか」を明示することも有効です。
会社のビジョンや目的を伝える
「何のためにこの仕事をしているのか」がわからないと、部下はやりがいを感じにくくなります。このような状況に陥ることなくモチベーションを向上させられるよう、企業のビジョンや仕事が社会にどのような影響を与えているかを社内で共有し、部下にも伝えることが重要です。
たとえば、「とにかく売上を上げろ」のような、具体的な意義や目的の不明な指示はするべきではありません。また、会社の方針を頻繁に変更することも社員の混乱を招きます。会社の目標と個々の業務を結びつけ、「私たちは〇〇を目指している」と、定期的にビジョンを共有するとともに、管理職や上司自身がビジョンに共感し、言葉と行動で示すことが重要です。
これらのポイントを意識せずに接すると、部下は「評価されていない」「成長できない」「この仕事には意味がない」と感じ、モチベーションが低下してしまいます。上司として、部下のモチベーションを引き出し、長期的な成長を促す関わり方を意識することが大切です。
まとめ
モチベーション管理とは、個人やチームが目標を達成するために持つ原動力や意欲を高め、維持することを指し、企業の生産性向上や人材定着に不可欠な要素です。適切な評価やフィードバックを行い、働きがいのある環境を整えることが、社員のモチベーションの維持につながり、生産性の向上や離職率の低下といった効果を生み出します。モチベーション管理においては、部下に対する上司の接し方も重要で、傾聴や公平な評価、明確なビジョンの共有などが求められます。

この記事を担当した人
PeopleX コンテンツグループ
人事・労務・採用・人材開発・評価・エンプロイーサクセス等についての用語をわかりやすく解説いたします。
これまでに出版レーベル「PeopleX Book」の立ち上げ、書籍『エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針』の企画・編集、PeopleX発信のホワイトペーパーの企画・編集などを担当しました。
- 株式会社PeopleXについて
- エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発・運営をはじめとした、新しい時代に適合したHR事業を幅広く展開する総合HRカンパニーです。