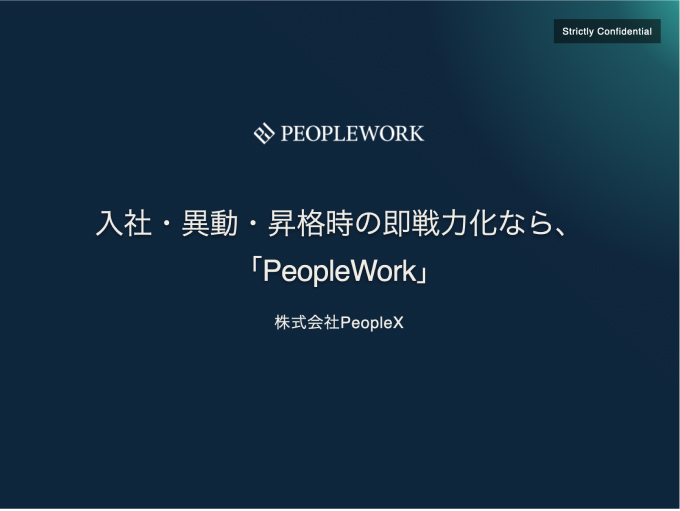2025.05.13
新入社員研修カリキュラムの作り方|実施する目的や主な内容、成功させるポイントを解説
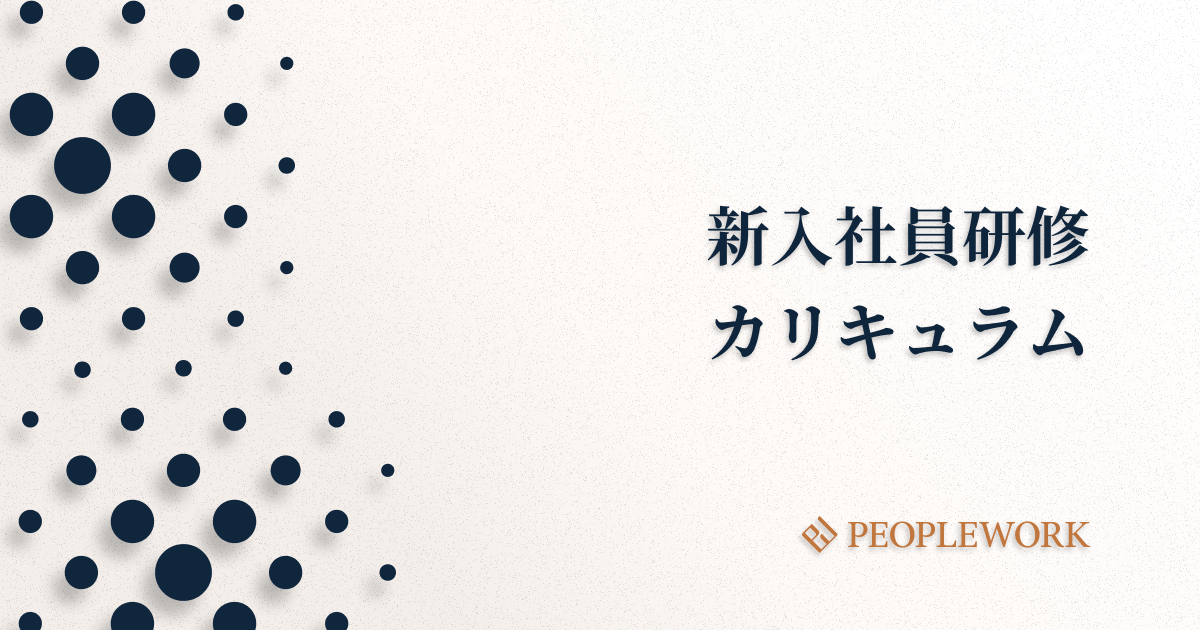
新入社員研修カリキュラムは、新入社員が業務に必要な知識やスキルを身につけ、スムーズに業務を行えるようにするために重要です。カリキュラムを作成することで、効率的な研修を行うことができ、研修の質を維持できます。
この記事では、新入社員研修カリキュラムを作成する目的やカリキュラムの主な内容、作り方について解説します。
新入社員研修カリキュラムとは
新卒の新入社員を迎え入れた際、社会人としての基本的なビジネスマナーと業務に必要なスキルを身につけ、業務を円滑に進められるようになってもらうことを目的とし、多くの企業で新入社員研修が行われます。
また、新入社員研修には、企業文化の理解を促進したり、社会人としての意識を高めたりするという役割もあります。
この新入社員研修をスムーズに進め、研修の効果をあげるためには、適切な新入社員研修カリキュラムの作成が必要です。
カリキュラムで新入社員に必要な知識・スキルを可視化すれば、何を優先的に学んでもらうかを明らかにでき、研修を行う側・受ける側双方にとって、意義のある研修になるでしょう。
新入社員研修カリキュラムを作成する目的
新入社員研修に際してカリキュラムを作る目的は、主に次の4点です。
- 研修の全体像を把握するため
- 組織の目標と齟齬のない研修を実施するため
- 効率的な研修を行うため
- 研修の質を維持するため
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
研修の全体像を把握するため
新入社員研修カリキュラムを作成する目的のひとつは、研修のプロセスや全体の流れを明らかにすることです。カリキュラムを作成することで、最終的なゴールと、ゴールへ向けて必要な内容からなる、研修の全体像を把握することができるでしょう。
これらが明確に示されていると、新入社員は習得内容やゴールを把握した上で研修を受けることができ、研修担当者は進捗を管理しながら不足なく研修を進めていくことができます。どの段階でどのような知識やスキルを身につけるかが、誰にとってもひと目でわかるようなカリキュラムを作成しましょう。
組織の目標と齟齬のない研修を実施するため
新入社員研修は、組織の目標を達成するために必要な人材を育てるはじめの一歩であり、研修内容が組織の目標に沿わない方向に進むことのないよう適切に実施されることが大切です。
組織の目標を念頭に置いたカリキュラムを作成することで、研修で身につけてもらう知識やスキルを組織の目標と連動させることができます。組織の目標を早い段階で共有し、目標達成に向けての意欲向上や貢献を促すこともできるでしょう。
効率的な研修を行うため
新入社員研修カリキュラムの作成は、効率的な研修を行うためのものでもあります。限られた時間内で最大限の成果を得るためには、優先順位をつけ、最低限身につけてもらいたい知識やスキルから優先的に習得してもらわなければなりません。
そのためには、 優先度の高い内容を中心としたカリキュラムを作成し、適切なスケジュールの下で研修を進めていくことが必要です。
研修の質を維持するため
研修の質を維持するためにも、新入社員研修カリキュラムの作成が必要です。新入社員研修は新入社員が入社した際に実施しますが、実施の度に研修内容が異なることは、入社時に必要な一定・共通の内容を習得してもらうという観点から望ましくありません。
新入社員研修は、年度や担当者が変わっても、一定の質を維持することが大切です。そのためには、長く活用できる汎用性の高いカリキュラムを作成することが求められます。
新入社員研修カリキュラムの主な内容
新入社員研修カリキュラムは、主に次の5つの内容で構成されます。
- 社会人へのマインドセット
- ビジネスマナー
- 企業に関する理解
- コミュニケーションスキル
- コンプライアンス
カリキュラムに盛り込む内容について、詳しく解説します。
社会人へのマインドセット
新入社員研修カリキュラムの内容として、社会人へのマインドセットは欠かせません。マインドセットとは、考え方や価値観、行動パターン、思考の癖などを指します。
社会人へのマインドセットは、これまでの生活における固定観念を一度リセットし、
社会人として自覚を持てるようにするために行います。
新入社員に社会人の価値観を一方的に押しつけるのではなく、社会人としての責任や環境の変化を理解してもらい、社会人の自覚をもって行動するための意識改革と捉えることが大切です。
ビジネスマナー
ビジネスマナーは、新入社員が社会人として円滑に仕事をこなすために必要とされる基本的なスキルです。
主に、次のような内容で構成されます。
- 身だしなみ
- 言葉遣い
- 挨拶の仕方
- 名刺交換の仕方
- 来客・電話対応
- ビジネス文書・ビジネスメールの作成
社会人にふさわしい身だしなみにすることや、正しい敬語を使い、好印象を与える挨拶をすることなどが挙げられます。
正しいビジネスマナーを身につけることで、顧客や取引先と良好な関係を築くことができ、業務を円滑に進められます。
企業に関する理解
新入社員研修では、企業に関する理解を深めてもらうことも必要です。そのために、次のような内容を習得してもらいます。
- 企業理念
- 事業内容
- 自社が手がける商品・サービス
- 職場のルール
企業の価値観や考え方、職場のルールについて理解することで、新入社員は組織における自分の役割を把握できます。既存社員と方向性を揃え、業務に取り組むことができるでしょう。
コミュニケーションスキル
業務を円滑に進めるためには、コミュニケーションスキルも必要です。そのため、新入社員研修では、ビジネスで必要なコミュニケーションスキルを教えます。
具体的には、次のようなコミュニケーションスキルです。
- 相手が伝えたいことを理解する
- 情報を正しく聴き取る
- 言いたいことを的確にわかりやすく伝える
コミュニケーションスキルを身につけることで人間関係が良好になり、周囲と協力しながら業務をスムーズに進めることができます。
コンプライアンス
組織の一員として働く上で、コンプライアンスの理解は重要です。コンプライアンスとは「法令遵守」を意味するものですが、企業において遵守すべきは、法令だけでなく、内容は多岐にわたります。
業種に関係なく新入社員研修で共通して取り上げるべきコンプライアンスの内容は、次のとおりです。
- 情報セキュリティ
- ハラスメント防止
- 社内規程や就業規則
- 法令遵守
- 企業倫理や社会的ルール
新入社員研修でコンプライアンス研修が必要な理由は、社会人としての基本的なルールや価値観を早い段階で身につけるためです。コンプライアンス研修では、法令遵守はもちろん、職場での適切な言動や社内ルール、情報の取り扱いなどを学びますが、これらに関する知識がないまま業務に入ると、無自覚にルールに反する行為をしてしまうリスクがあります。そのため、入社後すぐにコンプライアンスの基礎を学ぶことが大切です。
新入社員研修カリキュラムの作り方
新入社員研修カリキュラムを作成することで、全体像を把握しながら、均質で効率性の高い研修を実施することが可能となりますが、実際に作成する際は、次のような流れで行います。
- 関係部署にヒアリングをする
- 目標を設定する
- 具体的な研修内容・育成方法を決める
- スケジュールを作成する
各手順について詳しく解説します。
関係部署にヒアリングをする
新入社員研修カリキュラムを作成する際は、関係部署へのヒアリングを行いましょう。各部署で、新入社員研修が終わった時点でどのような知識やスキルを身につけておいてもらいたいと考えているか、具体的に理解しておくことが大切です。
管理職へのヒアリングにより、新入社員研修カリキュラムに取り入れるべき内容と、配属後にOJTで学ぶべき内容との棲み分けをすることもできるでしょう。
また、社歴の浅い若手社員にヒアリングをすると、実際に研修を受けて抱いた感想や意見、研修で良かったところ、改善してほしいところなどのフィードバックを受けることができ、カリキュラムの改善を図れます。
目標を設定する
新入社員研修は、新入社員に必要な知識やスキルを身につけてもらうために行います。その目的を達成するためには、具体的な目標設定が必要です。
自社にはどのような人材が必要で、そのために新入社員をどのように育成するのか、組織としての詳細な目標を設定します。これにより、どのような知識やスキルの習得が必要なのか、新入社員にとっての目標も明確となるでしょう。このとき、新入社員の目標と組織の目標にずれがないようにすることが大切です。
具体的な研修内容・育成方法を決める
目標を設定し必要な知識やスキルを洗い出すことで、知識やスキルの習得に必要な研修内容や育成方法を決めることが可能となります。目的と内容に応じて、座学やeラーニングなどでインプットをするか、演習やディスカッションを取り入れるかなどを決めていきましょう。
また、研修の効果を高めるためには、研修の目的や目標について、新入社員と共有することも大切です。目的や目標を把握することで、新入社員はより主体的に研修を受講できるでしょう。
スケジュールを作成する
研修内容と配属日に応じて、研修期間内の詳細な日程を定めましょう。研修期間自体の長さも、研修内容を無理なく終えられるよう、必要な場合は調整できるとよいでしょう。
研修期間中、どの内容にどの程度の時間をかけるか、どの順番で実施するか、といったことを決めていく必要がありますが、総論や一般的な内容から始め、現場で必要なより具体的な内容へ進んでいく、といった工夫があるとよいでしょう。座学、演習、外出など、複数の実施形式がある場合、新入社員の負担が少なくなるよう配慮することも望ましいといえます。また、会議室の手配や講師の予定の確保なども忘れず並行して行いましょう。
新入社員研修を成功させるカリキュラムを作るポイント
ここまで見てきたように、新入社員研修を成功させるためには、カリキュラムが重要な役割を果たします。
ここでは、新入社員研修を成功させる上で意識しておきたい、カリキュラムを作る際のポイントを解説します。
アウトプットの機会を設ける
新入社員研修では、座学によるインプットが多くなりがちですが、学んだ知識やスキルをアウトプットすることも大切です。
ロールプレイングやグループディスカッションなどアウトプットの機会を用意することで、新入社員は研修で学んだことが身についているかどうかを確認することができます。アウトプットを通じて理解が不足している部分を把握することで、新入社員自らブラッシュアップを行うこともでき、研修効果を高められるでしょう。
カリキュラムを詰め込みすぎない
研修では、カリキュラムの詰め込みすぎに注意が必要です。限られた期間の中で、業務に必要なすべての知識・スキルを習得させることは難しいでしょう。多くの内容を詰め込むのではなく、学ぶ知識・スキルの量は少ないとしても、優先度が高いものを着実に身につけてもらうほうが、より高い効果が期待できます。
研修期間の中でどのような内容を学んでもらうかを精査して、無理のない計画を立てましょう。
フィードバックを行う
研修の実施後は、振り返りの場を作り、フィードバックを行うことが大切です。
新入社員が研修を通して知識やスキルを十分に身につけられているか否かを確認し、本人に対しフォローやフィードバックを行いましょう。適切なフォローやフィードバックがなされることで、新入社員はより主体的に業務に取り組めるようになり、成長を促すことにつながります。
また、人事担当者は各部署の管理職と連携することで、研修の効果測定を行うこともできます。研修で実施した内容を伝えるとともに、現場での新入社員の仕事ぶりについて報告してもらうことで、カリキュラムが適切であったかを確認できるでしょう。加えて、研修に関わった社員や新入社員からのフィードバックも受け、問題点があれば改善を行うことにより、より良いカリキュラムにしていくことができます。その際、業務改善に有効なフレームワークであるPDCAを活用するとよいでしょう。
まとめ
新入社員研修を成功させるためには、カリキュラムの作成が必要です。カリキュラムを作成することで、研修の全体像を把握でき、効率的な研修を実施することができます。カリキュラムを作成する際は、関係部署にヒアリングし、新入社員に求める人物像について、具体的な目標を設定しましょう。
新入社員研修を成功させるカリキュラムを作るには、アウトプットの機会を設けることや、カリキュラムは詰め込みすぎずに優先度の高い内容に絞り込むことも大切です。

この記事を担当した人
PeopleX コンテンツグループ
人事・労務・採用・人材開発・評価・エンプロイーサクセス等についての用語をわかりやすく解説いたします。
これまでに出版レーベル「PeopleX Book」の立ち上げ、書籍『エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針』の企画・編集、PeopleX発信のホワイトペーパーの企画・編集などを担当しました。
- 株式会社PeopleXについて
- エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発・運営をはじめとした、新しい時代に適合したHR事業を幅広く展開する総合HRカンパニーです。