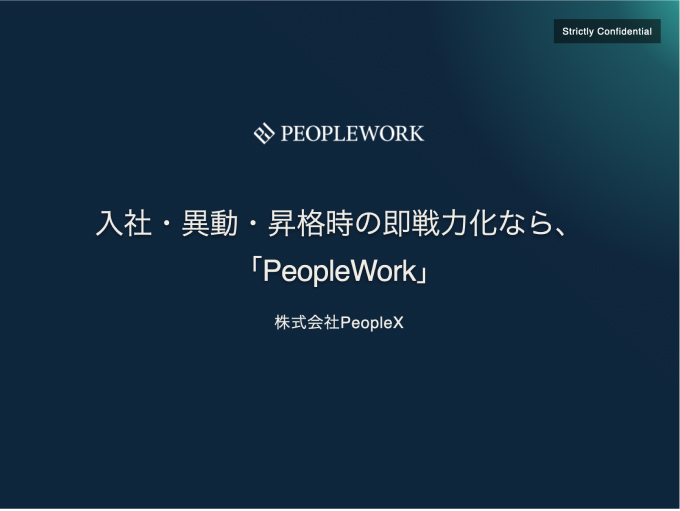2025.05.13
組織マネジメントとは? 現代の管理職に求められる能力とポイントを解説

物事の不確実性が高く未来の予測が難しいビジネス環境の中で、マネジメントに求められる役割も変化しています。これまでは、管理職が部下を管理統制するマネジメント手法が一般的でしたが、現代においては、目標達成に向けてチーム全体で協働していくようなマネジメントが必要となっているのです。
この記事では、現代における組織マネジメントの目的や重要性、導入する際に必要な事柄やポイントを解説します。
組織マネジメントとは
組織マネジメントとは、組織を円滑に運営するための手法のことで、「ヒト・モノ・カネ・情報」の4つの経営資源をどのように分配し、組織として機能させていくかが組織マネジメントの本質です。組織マネジメントを通して、組織の目標の達成を目指します。
組織マネジメントを主導するのは、管理職以上の役職者です。部長と課長のように役職が異なっても、「企業が利益をあげて事業を継続させるために必要な経営資源をマネジメントする」という根幹は変わりません。
組織マネジメントの目的や重要性
組織マネジメントの目的は、限りある経営資源を管理することにより、組織目標を達成することです。
経営資源は「ヒト・モノ・カネ・情報」の4つで成り立ちますが、中でも「ヒト」のマネジメントは重要なポイントといえます。「モノ・カネ・情報」を動かすのは「ヒト」であり、組織が目指すべきゴールへ向かって邁進するためには、「ヒト」の力が不可欠だからです。
「ヒト」のパフォーマンスはその時々の感情や心身の状態などに影響を受けやすく、マネジメントは一筋縄ではいきません。しかし、効果的な組織マネジメントを実現するためには、注力して管理すべき経営資源でもあります。
組織マネジメントとリーダーシップ
組織マネジメントは、リーダーシップと混同されることがあります。リーダーシップは「統率力」や「指導力」などの意味を持ち、組織の目指すべきゴールを示してチームを先導するスキルのことです。管理職だけに求められる力と認識されることもありますが、実際には、立場を問わずすべての社員が発揮すべき力です。
これに対して組織マネジメントは、組織目標を達成するための戦略を立て、経営資源を適切にマネジメントすることで課題解決を図ることを目的としており、役割を担うのは管理職以上の役職者に限定されます。
組織マネジメントを通して設定した仕組みを現場で実行するためには、リーダーシップを発揮できる人材が必要となります。
時代で変化する組織マネジメントの形
組織マネジメントの概念自体は、新しいものではありません。しかし、現代の組織マネジメントと従来の組織マネジメントでは役割や視点が異なるため、注意が必要です。
従来の組織マネジメントは、管理職などの上位層の意思決定を下位層へ伝達し、下位層はその命令に沿って動く形式でした。下位層は自分の考えで課題解決に取り組むことよりも、上司の指示や命令に忠実に行動することが重視されたのです。
しかし、現代は、少子高齢化による人手不足の深刻化や働き方の多様化、デジタル化やグローバル化の急速な進展などにより、ビジネスをめぐる環境変化が激しくなっています。このような時代において、従来のような上意下達型のマネジメント方法では変化のスピードについていくことが困難です。
そのため、現代の組織においては、さまざまな変化にも早く柔軟に対応できるよう、上層部の指示や命令を待って行動するのではなく、課題や目標を組織全体で共有し、一人ひとりが自身の力を発揮しながら自律的に行動することが求められます。組織マネジメントでは、このような組織の実現を目指して、管理職が組織の目指すべき方向性を示し、メンバーの力を引き出しつつ、ともに目標達成に向けて行動していけるよう組織をまとめていくことが重要となります。
組織マネジメントを導入するメリット
組織マネジメントを導入するメリットは、以下の3点です。
- 生産性向上
- 管理職の負担軽減
- 個別のマネジメントの実現
現代型の組織マネジメントが有効に機能すると、社員それぞれがスキルや経験を十分に発揮できるようになり、組織全体の生産性が向上します。
メンバーが自律的に行動できる組織が実現すれば、管理職はマネジメントに多くの労力を割く必要がなくなり、時間や気持ちに余裕が生まれるでしょう。
また、近年では多様な雇用形態や価値観の人が同じ職場で働くことがめずらしくなく、従来のような一元的なマネジメントが効果を発揮しづらくなっています。
管理職が余裕を持って、部下個人のスキルや経験、価値観を重視した個別マネジメントに取り組むことで、働き方に柔軟性が生まれ、外部環境の変化に対応しやすい、強い組織づくりが実現します。
組織マネジメントに役立つ7つのフレームワーク
組織マネジメントを行う上では、世界的な戦略コンサルティングファームであるマッキンゼー・アンド・カンパニーが提唱したフレームワーク「7S」を押さえておきましょう。7Sを活用することで組織の経営資源や課題が明確になり、より効率的なマネジメントが実現します。
7Sとは、具体的に以下の7つです。
- 組織構造(Structure)
- 戦略(Strategy)
- システム(System)
- 人材(Staff)
- スキル(Skill)
- スタイル(Style)
- 共通の価値観(Shared Value)
これらは、「ハードの3S」と「ソフトの4S」に大別されます。それぞれの内容を詳しく解説します。
ハードの3S
ハードの3Sは、組織構造に関する経営資源を指します。組織改革を推進した場合、後述するソフトの4Sと比較すると変化が見えやすいことが特徴です。
ハードの3Sは、以下の3つの要素で構成されます。
- 組織構造(Structure)
- 戦略(Strategy)
- システム(System)
それぞれについて解説します。
組織構造(Structure)
組織構造(Structure)とは、組織の階層や指揮命令系統など、組織の土台となる要素のことです。業務の内容や目的別に組織を構成する「機能別組織」、事業部ごとに意思決定する「事業部制組織」、プロジェクト単位でチームを形成し、チームとして業務を遂行する「プロジェクト組織」の3つに大別されます。
戦略(Strategy)
戦略(Strategy)とは、組織の目標達成に向けた道筋のことです。企業が競争優位性を維持・向上させていくためには、不可欠な要素です。
企業が今後目指すべき方向性を考える「企業戦略」、企業戦略を実現するために具体的にどのようなビジネスを展開するかを考える「事業戦略」、事業運営のために必要な研究開発・生産・営業・マーケティングなどの機能を考える「機能戦略」の3つがあります。
システム(System)
システム(System)とは、情報システムのようなハード面のシステムに加え、目標管理制度や予算管理制度など、社内の基本的な制度も含むものです。人事評価制度や給与制度など、経営資源の「ヒト」を有効活用するために必要な仕組みも含まれます。
社内の制度を明文化することで、すべての社員が一定の基準に従って業務を遂行できるようになります。
ソフトの4S
ソフトの4Sは、「ヒト」に関する経営資源を指します。ハードの3Sと比較すると変化がわかりにくく、定着までに時間がかかることが特徴です。
ソフトの4Sは、以下の4つの要素で構成されます。
- 人材(Staff)
- スキル(Skill)
- スタイル(Style)
- 共通の価値観(Shared Value)
それぞれについて解説します。
人材(Staff)
人材(Staff)とは、組織に所属する人材のことです。企業活動のために不可欠であり、人材によってビジネスの成否が左右されると言っても過言ではありません。さらに、社員個々の能力や仕事に対するモチベーション、またそれらを向上させるために企業が行う取り組みも含まれます。
基本的に、人材の本質を深く理解することは難しい作業です。積極的にコミュニケーションを図り、本質を見極めた上で社員個々人が能力を発揮できる環境を用意することが大切です。
スキル(Skill)
スキル(Skill)とは、他社と比較して組織として優れているポイントのことです。営業力や技術力、マーケティング力などが含まれます。
優れたビジネス戦略を持っていても、スキルが伴わなければ組織目標を達成することは困難です。スキルが高い組織ほど、競争優位性を発揮してマーケットをリードしていけるでしょう。
スタイル(Style)
スタイル(Style)とは、経営方針や組織風土など、企業のカラーにあたる要素を指します。経営層や管理職のリーダーシップがどのように発揮されているか、トップダウンかボトムアップか、暗黙の行動規範が存在するかなどもスタイルの要素です。
組織マネジメントを行う際は、組織のスタイルを正しく把握した上で実行することが重要になります。
共通の価値観(Shared Value)
共通の価値観(Shared Value)は、組織理念・ビジョン・行動指針など、組織全体で共有され、企業経営の基盤となる価値観です。すべての社員が同じ価値観を共有することにより、事業活動をスムーズに進められます。
経営層と社員との間で温度差や理解度に差がないかどうかも、重要な観点です。
組織マネジメントで管理職に求められる能力やスキル
組織マネジメントを有効に機能させるためには、管理職が能力やスキルを身につけている必要があります。現代の組織マネジメントにおいては、管理職には特に以下のような能力やスキルが求められます。
- 目標設定力
- 計画遂行力
- コミュニケーションスキル
- 人材マネジメント力
- 評価力
- リスク管理力
管理職は、組織が一丸となって業務に取り組めるよう、組織としての目標を設定し共有することが必要です。現代においては、メンバーが自律的・主体的に行動できるよう、ビジョンを示し動機づけをしていく力が特に求められます。
そして、設定した目標から逆算し必要な過程や要素を洗い出した上で計画を立て、目標達成に向けて計画を着実に遂行していく力も要求されます。その際、メンバーと円滑にコミュニケーションをとれることも重要な要素です。
社員のスキルや適性を把握し最適な配置・育成を行う人材マネジメントも、組織全体のパフォーマンスを向上させる上で必要となります。また、メンバーを公平に評価するスキルも求められます。意欲が高く優秀な社員でも、正当に評価されなければやる気を失ってしまうでしょう。一人ひとりを正しく評価し、モチベーション向上につなげ、メンバーそれぞれの持つ能力を引き出すことが大切です。
さらに現代においては特に、社内のみならず外部環境の変化にもいち早く気づき、対策を講じられるリスク管理能力が求められます。リスクが顕在化する前に対策を立てておき、いざという時に迅速に行動を取れる体制を構築しておくことが大切です。
組織マネジメントを実現するためのポイント
組織マネジメントを実現するためのポイントは、以下の3つです。
- 目的を明確にする
- メンバーとの信頼関係を構築する
- リーダーとしての影響力の強さを考慮する
まずは、組織マネジメントの目的やビジョンを明確にします。目的やビジョンが不明確だと、メンバー各々が異なるゴールに向けて行動してしまい、チームとしての力を最大限に発揮できません。現代の組織マネジメントでは、メンバーの自律的な行動がポイントとなります。チーム全体でモチベーションを向上させ同じ目標に向かって進めるよう、管理職が率先してビジョンを示す必要があるのです。
また、経営資源の中でも重要なポイントとなる「ヒト」のマネジメントを効果的に行うために、メンバーとの信頼関係の構築を重視する必要があります。強固な信頼関係に支えられた組織は、困難な問題に直面しても互いに知恵を出し合いながら乗り越えていくことができるでしょう。
組織マネジメントを実行する中で、必要に応じて従来型のマネジメントをしなければならない局面があります。そのような場合は、管理職としての影響力の強さを考慮した上でメンバーに働きかけることが大切です。
まとめ
組織マネジメントは、組織を円滑に運営するための手法であり、経営資源を適切に管理し組織としての目標を達成することを目指します。
従来の組織マネジメントは、トップダウン型が主流でした。しかし、ビジネス環境の変化が激しい昨今、より効率的に成果をあげる仕組みの下で組織を運営していくことが求められます。
組織マネジメントを主導する管理職は、このような背景を理解した上で、目標やビジョンを共有し組織全体を牽引しながら目標達成に向けて行動していく必要があります。

この記事を担当した人
PeopleX コンテンツグループ
人事・労務・採用・人材開発・評価・エンプロイーサクセス等についての用語をわかりやすく解説いたします。
これまでに出版レーベル「PeopleX Book」の立ち上げ、書籍『エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針』の企画・編集、PeopleX発信のホワイトペーパーの企画・編集などを担当しました。
- 株式会社PeopleXについて
- エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発・運営をはじめとした、新しい時代に適合したHR事業を幅広く展開する総合HRカンパニーです。