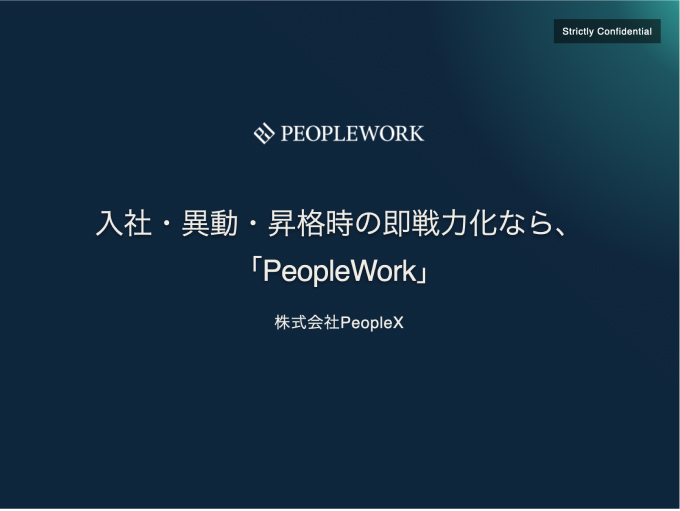人事労務
2025.04.08
人件費とは? 勘定科目や削減対策、適正か否かの判断方法を解説
- #人事労務

人件費とは、社員を雇用するためにかかる費用のことで、給与や賞与、社会保険料などが含まれます。事業継続に人件費は不可欠ですが、あまりにも高くなると経営を圧迫するため注意が必要です。
この記事では、人件費の勘定科目や削減対策、また、適正か否かを判断する方法を紹介します。
人件費とは
人件費とは、社員を雇用するためにかかったすべての費用のことです。給与や賞与、各種手当、社会保険料など、社員に支払う費用や雇用維持にかかる費用は、すべて人件費として分類できます。
人件費の範囲
人件費は、雇用する人すべてに関わる費用です。正社員や契約社員、パートタイムなど、雇用契約の下で働く人に支払う給与や賞与は、人件費にあたります。他方、委任契約を結ぶ役員に支払う役員報酬は人件費の範囲には含めないケースもあります。
また、派遣社員については、常勤の場合は人件費の範囲内としますが、臨時の場合は雑費と考えることもあります。社内で人件費の範囲を明文化し、ルールに沿って費用を区分けするようにしましょう。
人件費と労務費の違い
労務費とは、人件費のうち製品の製造に関わった社員に支払った費用のことです。工業簿記の用語で、製品の原価計算の際に用いられます。
一方、人件費は、社員に支払われる費用全般です。従事する業務を問わず、すべての社員に関する費用を指します。
人件費の勘定科目
人件費の勘定科目(取引の内容を分類・記録するために簿記で使われるもの)は主に次の8つです。
- 給与手当
- 専従者給与
- 役員報酬
- 賞与
- 法定福利費
- 福利厚生費
- 旅費交通費
- 退職金・退職給与引当金
それぞれに含まれる費用を紹介します。
給与手当
給与手当は、正社員やパートタイム、アルバイトの給与や各種手当を仕訳するときに用いる勘定科目です。どのような手当が設けられているかは企業によって異なりますが、通勤にかかった費用を支払う通勤手当や、配偶者や子どもなどを扶養している社員に支払う扶養手当、家賃の一部を支給する住宅手当などがあります。なお、通勤手当は福利厚生費として仕訳することもあります。
また、法定労働時間を超えて働かせた際に支払う時間外労働手当や、法定休日にやむを得ず出勤させた場合に支払う休日出勤手当もあります。
なお、通勤手当や扶養手当などは企業側に義務付けられた手当ではないため、金額は企業が自由に設定できますが、時間外労働手当と休日出勤手当は労働基準法の規定に従って支払わなければならない点に注意が必要です。
専従者給与
専従者給与とは、生計を一にする家族の従業員に支払う給与を仕訳する際に用いる勘定科目です。青色申告をし、青色事業専従者として届出をしている家族に支払う給与は、人件費として経費に含められます。
ただし、青色事業専従者として届出をしていない家族や、青色事業専従者の資格を満たさない家族に支払った給与は、経費として計上できない点に注意しましょう。
役員報酬
役員に支払う報酬は、役員報酬の勘定科目で仕訳をします。定期同額給与と事前確定届出給与、利益連動給与は損金算入が可能です。ただし、不当に高額と判断される部分については損金算入できない点に注意してください。
また、一般的に役員の契約形態は雇用契約ではなく委任契約のため、役員報酬は人件費には含めないケースもあります。特定の支払項目を人件費に含めるか否かは、あらかじめ決めておきましょう。
賞与
定期的な賞与(夏・冬のボーナスなど)や臨時賞与は、賞与の勘定科目で仕訳をすることが一般的です。ただし、賞与は給与手当として仕訳をしても問題ありません。帳簿を整理しやすいように勘定科目を使い分けましょう。
法定福利費
法律で定められている社会保険や労働保険の保険料のうち、会社負担分については、法定福利費の勘定科目で仕訳をします。社会保険料も労働保険料も社員を雇用する際には不可欠な費用であり、人件費として扱います。
福利厚生費
法定福利厚生のほかに、社員が快適に働ける環境を構築するために法定外福利厚生を設ける場合もあります。これにかかった費用は、福利厚生費の勘定科目で仕訳をします。たとえば、社員旅行やレクリエーションにかかった費用、結婚や子どもの誕生時に支払う祝い金、健康診断の費用などは福利厚生費として分類することが一般的です。
法定福利費との違いは、事業者が負担することが法律で義務づけられているか否かという点にあります。社会保険料や労働保険料は法律で義務づけられているのに対し、社員旅行の費用や祝い金などは法律では義務づけられたものではなく、企業の裁量に任せられています。
旅費交通費
旅費交通費は、社員の移動にかかった費用の仕訳に用いる勘定科目です。たとえば、出張時の交通費や宿泊費など、業務遂行のための移動や宿泊のための費用は、旅費交通費として会計処理を行います。
退職金・退職給与引当金
社員が退職する際に企業が支給する金銭については、退職金や退職給与引当金の勘定科目で仕訳をします。なお、退職時に金銭を支払う法律上の義務はないため、企業によっては退職金がないこともあります。
また、退職金の支払方法も企業の裁量に委ねられています。退職時にまとまった金額を支給する「一時金」や退職後に定期的に支給する「年金」、「一時金」と「年金」を併用するケースなどがあります。
人件費の削減対策
事業運営において人件費は欠かせない費用ではありますが、あまりにも多額になると経営を圧迫するおそれがあります。人件費を適正な金額に抑えるための対策をいくつか紹介します。
業務効率化を図る
業務時間を短縮することができれば、時間外労働や休日出勤、社員数を減らすことができるため、人件費を削減できます。業務効率化を図り、業務時間を減らしましょう。
たとえば、使用機会の多い書類はフォーマット化する、経費はすべてクレジットカードで支払う、請求書や発注書などは専用ソフトで一括作成するなどの対策により業務効率化を進められることもあります。
また、業務フローの見直しも必要です。業務手順や確認作業のタイミングを変えるだけでも、業務にかかる時間を短縮できることがあります。
アウトソーシングを活用する
すべての業務について社内人材だけで対応しようとすると、かえって業務時間が長引いたり、教育や研修にかかる費用がかさんだりすることがあります。業務によってはアウトソーシングを選択し、社外人材の労力や知見を活用するのも一つの方法です。
ただし、アウトソーシングは、必ずしも経費圧縮につながらない点に注意してください。特定の業務を外注することで社内人材の時間外労働や休日出勤を減らせる可能性はありますが、アウトソーシング費が割高で、かえって業務遂行にかかる費用が高額になるケースもあります。
アウトソーシングを利用するときには、メリットとデメリットを比較し、本当に依頼するべきかどうかを吟味するようにしましょう。また、費用面だけでなく、業務のクオリティや専門性、作業にかかる時間なども含め全体的な比較・検討をするようにしてください。
社員のパフォーマンスを向上させる
社内人材のパフォーマンスを向上させることも、人件費の削減につながります。まずは人材配置が適切かどうかを見直してみましょう。有能な人材でも、能力が発揮できる場所に配置されていない場合や、勤務時間や報酬・職位が適切でない場合は、本来の能力を発揮できません。
また、有能な人材を育てることも大切です。必要に応じて研修を実施し、意欲に応じてスキルアップできる仕組みを構築しましょう。
人件費が適正か否かを判断する方法
人件費が適正か否かは、次の数値から判断することが一般的です。
- 人件費率
- 労働分配率
それぞれの数値の求め方や判断方法を紹介します。
人件費率で判断する
人件費率とは、売上高に対する人件費の割合のことです。以下の計算式から求めます。
| 人件費率=人件費÷企業の売上高×100 |
人件費率の目安は、業種や業態によっても異なります。「中小企業実態基本調査(令和5年度)」で公表されている産業別の「労務費」と「人件費」を合算し、各売上高で割って算出したものが以下の表のとおりです。自社が属する産業の平均人件費率と比較してみてください。
| 産業 | 人件費率(%) |
|---|---|
| 全体 | 16.1% |
| 建設業 | 16.7% |
| 製造業 | 19.4% |
| 情報通信業 | 30.6% |
| 運輸業/郵便業 | 30.0% |
| 卸売業 | 6.4% |
| 小売業 | 12.9% |
| 不動産業/物品賃貸業 | 11.6% |
| 学術研究/専門/技術サービス業 | 32.9% |
| 宿泊業/飲食サービス業 | 31.7% |
| 生活関連サービス業/娯楽業 | 15.8% |
| サービス業(他に分類されないもの) | 42.3% |
このように人件費率は業種や業態によっても異なりますが、企業規模によっても異なります。そのため、上記の人件費率よりも高い場合でも、必ずしも人件費がかさんでいるとは判断できません。あくまでも人件費率を見直す上での参考としてください。
参照:中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年度決算実績)
労働分配率で判断する
労働分配率とは、企業が生み出した付加価値額に対する人件費の割合のことです。以下の計算式で求めます。
| 労働分配率=人件費÷付加価値額×100 |
付加価値額とは、売上から人件費を含む諸経費を差し引いて求めた粗利です。労働分配率が高い企業は粗利に対して人件費が高いと考えられるため、社員の満足度も高いと考えられます。そのため、労働分配率を低く抑えすぎず、なおかつ高くなりすぎないように調整することが必要です。
経済産業省が2025年1月に公表した「2024年経済産業省企業活動基本調査速報」によれば、産業全体の労働分配率は46.6%でした。産業ごとに大きな違いはなく、いずれも40%台です。
| 産業 | 労働分配率(%) |
|---|---|
| 全体 | 46.6% |
| 製造業 | 46.3% |
| 卸売業 | 43.2% |
| 小売業 | 46.9% |
参照:2024年経済産業省企業活動基本調査速報(2023年度実績)
まとめ
人件費は事業を行う上で不可欠な費用ですが、売上高と比較して高すぎる場合は利益効率が悪いと判断でき、見直しが求められます。しかし、人件費を抑えすぎると、社員の満足度が低下する要因となり、生産性が低下するおそれもあります。人件費率や労働分配率の目安も参考に、適正な額となるよう検討・管理するとよいでしょう。また、人件費そのものだけでなく、社員個人のパフォーマンスや配置にも注目することも大切なポイントです。

この記事を担当した人
PeopleX コンテンツグループ
人事・労務・採用・人材開発・評価・エンプロイーサクセス等についての用語をわかりやすく解説いたします。
これまでに出版レーベル「PeopleX Book」の立ち上げ、書籍『エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針』の企画・編集、PeopleX発信のホワイトペーパーの企画・編集などを担当しました。
- 株式会社PeopleXについて
- エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発・運営をはじめとした、新しい時代に適合したHR事業を幅広く展開する総合HRカンパニーです。